|
ふんぞりかえったゾウリムシ
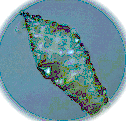
医局説明会と称して、医学生を飲みに連れていく。入局勧誘が目的であるが、学生相手に医局の裏話をしたり、診療や研究での愚痴を聞いてもらっている。
「先生はどうして、整形外科を選んだんですか?」
隣に座っている学生が、分厚い眼鏡を通してのぞき込んできた。かなり酔っているようだ。
「そうだなあ。いろいろ理由はあるけど、しいてあげれば『ふんぞり返ったゾウリムシ』かな。」
「は?」
眼鏡の奥の爬虫類のような目が一瞬ひるんだ。その虚をついて私は十五年前のあの日を懐かしんだ。
「先生ねえ、やっぱりこれからは整形の時代よ。うん。」
アメリカ留学から帰ったばかりのT先生は、語尾を巻き舌にしながら頷いた。
「はあ、そうですか。」
学生の分際で、先生と呼ばれた面映ゆさで照れながら答えると、これまた六十年代のアメリカから抜け出してきたようなK先生が、リーゼントの髪を撫でながら、
「高齢者が増えて、足腰が痛くなる。スポーツが盛んになり、けががふえる。まあ整形しかないでしょうね。これからは。あ、おねえさん、ビールこちらおかわり。」
ここは市内のとある居酒屋。夏休み、国家試験の勉強から少し解放され、アルコールのピッチが早い。
「先生も、お酒強そうね。うちの医局にもお酒の好きなのが多くて。」
ポマードの乗りが悪いのか、しきりに髪形を気にするK先生。
「親分も好きだしね。」
「ボスは、むちゃな飲み方はしないけど、M先生、かれはすごい。」
ボスとか親分はどうも教授のことを言っているらしい。医局というのは名ばかりで、わたしがこれから入るかもしれないところは、○○組といった組織に近いのではないかと、刹那不安がよぎる。
「老子だったか荘子だったか、チョウチョになった夢を見て、チョウチョになった自分と夢を見ている自分、どちらがほんとの自分なのかわからなくなるといったものがあるじゃない。M先生はちょうどそれと同じで、酔った自分と、しらふの自分、どちらがほんとの自分かわからなくなるときがあるんじゃないかな。」
「周りも同じよ、酔ったM先生と、しらふのM先生、どちらがほんとのM先生かわからなくなる。」二人の整形外科医は顔を見合わせて、やもりが鳴くようにケケケケケと笑った。
「先生は、趣味は何? 絵? 自分で描くの? 油絵とか水彩とか。」
「ええ、多少は。下手ですけど一応美術部に席をおいてました。」
「じゃあ美的センスがあるんだ。これって大切よ、整形外科医にとって。ねえT先生。」
「そうそう、整形の場合、手術の結果が、すぐに術後のレントゲン写真にでるわけよ。だからどうしたら美しい術後写真を残すか。これが腕の見せ所なわけ。」
「美にこだわる外科医、それが整形外科医。なんてね。」
「ボスもよく言うじゃない。美しい物は機能的で、機能的なものは美しいって。」
「親分も絵に関してはうるさいよね。今日の術後検討会でG先生が内反足の手術記録で描いた子供の足。『ふんぞり返ったゾウリムシだね。』って。」
「いやーあれはうけた。言い得て妙、G先生も頭を掻くしかない。」
二人の整形外科医は、G先生の頭を掻く癖をまねて、大声で笑った。
『美にこだわる外科医』、そのフレーズが妙に私の美意識を捕らえた。そして『ふんぞり返ったゾウリムシ』、これは単なる形容や揶揄を超えた、シニカルでシュールな文学表現ではないか! こんなことのできる親分を持つことも悪くない。肌に残った夏の日差しが酔いのほてりに置き換わり、居心地のいい安手の居酒屋で、わたしの心は整形外科入局へと傾きかけていた。
目次へ戻る / 前のエッセイ / 次のエッセイ
|